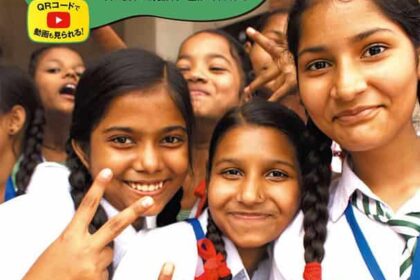個人主義と集団主義のバランス<イスラムはどんな宗教?>
イスラム教のどんな点が魅力的か?と聞かれたら「個人主義と集団主義がバランスとれている」点だと思います。
人間は時に一人になりたい生きもの。でもずっと一人では寂しい。誰かとつながっている安心感も欲しい。
そんなワガママをイスラムは満たしてくれる宗教なのです。
一体感:「彼女は同じイスラム教徒だから」
イスラムでは同じ信者同士の一体感が生まれます。それについて、よく思い出す出来事があります。
かつてエジプトに住んでいた時、私はエジプト→イエメン→エチオピア→スーダン→エジプトと周遊旅行をしました。
そしてスーダンに滞在していた時、イエメン男性とスーダン人女性と行動を共にする機会がありました。たまたま旅のルートが同じだったからです。
イエメン人男性は20代。陸路でエジプトを目指していました。エジプトからリビアに行き、仕事を見つけるつもりだったのです。
スーダン人女性は40代。なぜ旅をしていたのかは、今は覚えていません。
驚いたのは、イエメン人男性がスーダン人女性の飲食費を全て出していることでした。2人は家族でもありませんし、イエメン人の彼は裕福でもありません。
彼にそのことについて聞くと 「彼女は同じイスラム教徒だから」という答えが。
同じ信者というだけで、家族同様の強いつながりが生まれる。
イスラムってなんだろう? 私がイスラム教について強く興味を持った瞬間でした。
一体感を強める儀礼
イスラムには、信者同士が強いつながりを感じられる儀礼も数多く用意されています。
代表的なのはメッカ巡礼です。毎年決まった時期に、全世界から何百万人ものイスラム教徒が集まって、同じ儀礼を行います。
ラマダン月の断食は家族とのつながりを深める機会です。ふだんは別々に食事する家族も、ラマダン中は早く仕事を終えて、家族と同じテーブルにつきます。近くに住む家族や親戚がしばしば集まって会食します。
モスクや町中では、裕福な人が無料で食事を提供する「神の食卓」というテーブルが設けられ、誰でもそこで食事することができます。だから連日知らない者同士の会食が行われているようなものです。
そして金曜日の集団礼拝(男性のみ)。金曜日の昼の礼拝は最も大切なものとされ、男性はモスクに集まって合同で礼拝します。
礼拝の文句は、全世界のイスラム教徒で同じです。インドネシア人もパキスタン人もモロッコ人も、唱える言葉は同じアラビア語です。
礼拝の最後に、「アッサラーム・アレイクム・ワ・ラハマットット・ラーヒ(神の平安と恩寵があなたたちにあるように)」という句を2度唱えます。これは全世界のイスラム教徒との連帯を願う言葉です。
信者は「同じルール」に沿って生きる仲間
イスラム教は日々の生活上のルールを定めています。
ということは、つまりイスラム教徒たちはそれぞれ「同じルールに沿って生きる仲間」だということです。
だから家族同様のつながりが生まれるのです。
個人主義:信仰は個人と神との関係
一方で、イスラムはとても個人主義です。
信仰はあくまで個人と神との問題。他人にとやかく言われることはありません。
礼拝をしていなくても、ラマダン月に断食していなくても、他人がそれを批判することはタブーです。
「イスラム教では、信仰は神と個人の契約という考えに立ちます。それぞれが神と直接に相対しますから、ルールを守る度合いも人それぞれで、要は自分の気持ちの問題です。たとえばヒジャブを被っていない人に対して、「ヒジャブかぶってないじゃん」と非難したりするのは、イスラムの教えをちゃんと理解できていない人です。他人のことは他人のこと。」
(「日本人に知って欲しいイスラムのこと」)
信者との一体感を感じられる一方、個人の信仰はあくまで本人の個人の問題。
人は自分の信仰について、他人にとやかく言われたくないという気持ちもあります。この点、イスラム教は「他人の信仰に口出ししない」という気楽さがある。
同時に信者同士の結びつきを感じられる仕組みも用意されている。
人は時に一人になりたい生き物。でもずっと一人はさみしい。時にはわいわいみんなと楽しみたい。
個人主義と集団主義の融合。これがイスラムが多くの人々に受け入れられてきた理由ではないかと思います。
★「イスラム流幸せな生き方」
中学生でもわかるイスラム入門書。なぜ世界中でイスラム教徒が増え続けているか?がわかります。