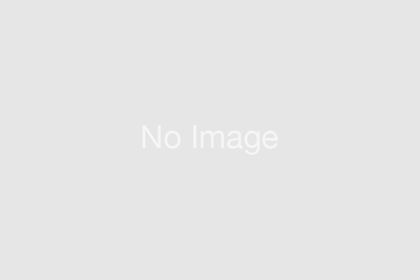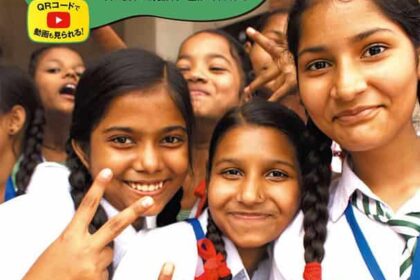自分を好きになる力

エジプトの結婚式で民族舞踊を踊るダンサー。お腹が出ているのは妊婦をモチーフにしているため。「新婦が早く赤ちゃんに恵まれるように」という意図が込められている。
私が旅に出て「幸せ」について考えるようになったのは、ある年齢まで「自分は幸せではない」と思っていたからです。
私の高校時代までは、決して楽しいものではありませんでした。何も不自由ない家庭で育ち、勉強もそこそこできたものの、内気で人付き合いが下手で、友達もほとんどいませんでした。
いつも楽しそうに談笑しているクラスメートを横目で見ながら、その輪の中に入っていけず、さみしい思いをしていました。幸福度も自己満足度も恐ろしく低い生徒でした。
自分を変えるためにインドネシアへ
そんな自分を変えたくて、大学3年の時に思い切って大学を休学し、インドネシアに一人旅に出たのです。それまでに団体旅行でアメリカと台湾に行ったことがありました。
今度は一人で行ってみよう。それもなるべく長く。知っている人もいない、言葉もわからない見知らぬ土地で旅をすれば、自分を変えられるかもしれない、そんな安直な思いからです。
乗り物の中で現地の人と知り合うと、よく声をかけられました。「どこから?」「ひとり?」。大学の授業でちょっとかじったインドネシア語で受け答えすると、向こうは言葉でできると勘違いし、ばーっと話し出す。何を言っているのか、さっぱりわかりません。
とりあえず相づちを打っていると、「これからうちに来ない?」となります。行けば「今夜はここに泊まりなさい」となり、泊まれば「好きなだけいていいよ」となる。こうして見ず知らずの人の家に泊まること20数軒。
知らなかった自分を発見
「世界にはこんな人がいるのか」と衝撃を受けました。もっとおどろいたのは、「自分に対して」でした。友達が全くいなかった内気な自分。その私が、知り合ったばかりの他人の家に平気で泊まっている。こんな内気な自分でも、受け入れてくれる人がいる。
日本では、自分は内気で生きる価値がないとすら思っていましたが、そんな考えは、どこかに消し飛んでいました。そして新たな自分を発見したように思いました。
しかしこの旅で自分が変わったのかといえば、今もあいかわらず内気で人見知り、人と話すのが苦手です。
自分への見方を変えてみる
変わったことがあるとしたら、自分の性格への「見方」です。
以前は内気を「短所」と思っていましたが、今は「個性」の1つだと思えるようになりました。内気は悪いところばかりではありません。内気だからこそ、旅では現地の人に頼りなく思われ、家に呼ばれたのかもしれません。もし社交的でガンガン話しかけるタイプなら、逆にあやしまれていたかもしれません。
話すのが苦手だから、とにかく相手の話を聞くことにした。それが相手にひょっとしたら好印象を与えたのかもしれません。
短所は見方を変えれば長所にもなります。話すのが苦手な人は、多くの場合、聞き上手です。聞き上手は人付き合いの上でメリットです。たいていの人は自分のことを聞いてもらいたいものです。
自分の持って生まれた性格と仲良くする
誰にも性格上でのコンプレックスがあると思います。でも自分の持って生まれた性格は、容易に変えることはできません。変えようとせず、それを受け入れ、うまく付き合っていく。内気は内気なりに楽しく生きられる場所、ラクに生きられる方法を見つけて行くことです。
誰にも得意、不得意があります。数学ができないのも個性です。むりに直そうとせず、他の得意なことで頑張ればいい。勉強ができなければ、スポーツや好きな趣味で頑張ればいいのです。
今の日本社会は、短所は克服せよ、自分に満足せずに上を目指せ、と背中を押します。でもそうやっていたら、生きずらくなるばかりです。自分を受け入れ、今の自分で満足することです。それが幸せに生きる秘訣です。
人生は、自分の短所や不得意を直しているほど、長くはない。自分の「好き」を追求し、かけがえのない自分の個性を尊重し、自分が生きやすい道を探って行く。それが幸せに生きる道ではないでしょうか。